糖質の正しい理解が、パフォーマンスと健康を変える
「糖質は太る」
「糖質制限が健康にいい」
そんな声がある一方で、実際には糖質が体を動かす主なエネルギー源であることは間違いありません。とくに筋トレや運動をしている人にとって、糖質の理解はパフォーマンスを大きく左右します。
この記事では、糖質の種類や代謝経路、果糖との違い、そして避けるべき糖質の種類まで、科学的な根拠をもとにわかりやすく解説していきます。
糖質は体のガソリン
糖質の貯蔵量は意外と少ない
体脂肪は数kg単位で蓄えられますが、糖質はその10分の1以下。主に次の3カ所に保存されます。
- 肝臓のグリコーゲン:約100g
- 筋肉のグリコーゲン:約300g
- 血液中のグルコース:約20g
このように貯蔵量が限られているため、日々の食事で補給する必要があります。
糖質が重要な2つの理由
糖質は主に2つの理由で不可欠です。
- 1つ目は、糖質がエネルギー(ATP)を作るための材料になります。脂質よりも早く使われるため、瞬発的な動きや高強度トレーニングでは特に重要です。
- 2つ目は、筋肉の分解を防ぐためです。糖質が不足すると、体は筋肉を分解してアミノ酸から糖を作る「糖新生」を行います。結果、筋肉量が減って基礎代謝も低下してしまうのです。
炭水化物と糖質の違い
「糖質=炭水化物」は間違い
炭水化物は「糖質」と「食物繊維」の総称です。糖質はエネルギー源になりますが、食物繊維は基本的に消化されず、エネルギーにはなりません。
また、一般的に糖質1g=4kcalとされていますが、実際に体内で使われるエネルギーは平均3.8kcal前後。これは消化吸収効率の差によるもので、栄養学的にはより正確な知識が求められます。
糖の種類とその分解
単糖類・二糖類・多糖類の違い
糖は構造により以下の3つに分類されます。
- 単糖類(例:ブドウ糖、果糖、ガラクトース)
- 二糖類(例:砂糖、麦芽糖、乳糖)
- 多糖類(例:デンプン、マルトデキストリン、グリコーゲン)
最終的には、消化酵素によってブドウ糖などの単糖に分解され、体内でエネルギー源として使われます。
ブドウ糖はどう使われる?
ブドウ糖が体内に入ると血糖値が上昇し、それに応じて膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンはブドウ糖を細胞内に取り込み、以下の流れでエネルギーへと変換します。
- 解糖系 → ピルビン酸に変換
- クエン酸回路 → 電子伝達系へ
- ATP(エネルギー)を生成
この代謝には、ビタミンB群(特にB1・B2・ナイアシン・パントテン酸)やミネラル(鉄、マグネシウムなど)が必須です。
ビタミンB群が足りないとどうなる?
糖をエネルギーに変換する「代謝酵素」は体内で作られますが、その働きには「補酵素」が必要です。補酵素とは、代謝を助ける栄養素であり、主にビタミンB群やミネラルが該当します。
特にビタミンB群は活性型に変換されないと効果を発揮しません。その変換には鉄や亜鉛、マグネシウムなどのミネラルが必要です。
つまり、糖を効率よく使いたいなら、ビタミンB群とミネラルを一緒に摂ることが不可欠なのです。

【バカにできない】ビタミンとミネラルが不足すると代謝は止まる!体調不良の原因と改善方法
糖質を代謝する際に必要な補酵素!補酵素の役割を持っているビタミンミネラルについてもっと詳しく知りたい方はこちらも読んでみてください
果糖(フルクトース)の代謝は注意が必要
果糖は小腸で代謝される?
これまで果糖は肝臓で代謝されると言われてきましたが、近年の研究では「小腸で90%以上代謝される」ことが明らかになっています。
これは「ケトヘキソキナーゼ」という酵素が小腸に存在するためで、ここで代謝された後に肝臓へ運ばれます。
果糖が引き起こす副作用とは?
果糖の代謝で問題になるのは、副産物です。
- 乳酸(過剰に産生されやすい)
- 脂肪酸(脂肪肝や内臓脂肪の原因)
- コレステロール(高脂血症リスク)
- 活性酸素とAGEs(終末糖化産物)
とくにAGEsは老化や糖尿病合併症の要因となる物質。中でも「グリセロアルデヒド型AGEs」は強い毒性を持つことがわかっています。
果糖ブドウ糖液糖には要注意!

清涼飲料水やお菓子、加工食品に含まれる「果糖ブドウ糖液糖」は、トウモロコシ由来のブドウ糖を人工的に果糖化したもの。ビタミンやミネラルが一切含まれておらず、代謝の過程で強い酸化ストレスを引き起こします。
日本人は平均で年間6.4kgも摂取していると言われており、コンビニやスーパーの商品ラベルを見て、「果糖ブドウ糖液糖」が入っていないかを確認する習慣が大切です。
フルーツは悪ではない
フルーツには果糖が含まれますが、同時にブドウ糖や食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなどの有用成分も豊富です。
たとえばバナナの糖は果糖とブドウ糖が半々。さくらんぼのように果糖比率が高い果物もありますが、極端に避ける必要はありません。
問題なのは「単離された糖(液糖など)」であって、自然な食品としてのフルーツはバランスの取れた栄養源です。
糖質制限のリスクと誤解
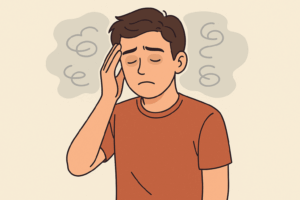
ケトジェニックダイエットのように極端に糖質を制限すると、以下のような問題が起こる可能性があります。
- 脳:基礎代謝のうち約20%は脳が消費(糖が主燃料)
- 神経組織や水晶体:糖しか使えない部位もある
- 長期的には神経障害、白内障、腎不全のリスクも
糖質は「完全にカットすべき」ものではなく、「量と質を調整すべき」栄養素です。
糖質は悪者ではない。使い方次第
糖質は、私たちの体と脳を動かす重要な燃料です。特に運動をする人、集中力を高めたい人、健康を維持したい人にとって、糖質の「質」と「摂取のバランス」を見直すことがパフォーマンスの鍵を握ります。
避けるべきは「果糖ブドウ糖液糖」などの精製糖であり、フルーツや全粒穀物などから得られる糖質は、むしろ積極的に取り入れる価値があります。
あなたの体が本当に必要としているのは、「正しい知識と選択」かもしれません。
