アルコールの酔いを抑えるには?栄養学から見るお酒との付き合い方
「お酒を飲むとすぐ酔ってしまう」
「翌日に残りやすい」
「体への負担が心配」
そんな悩みを持つ方にぜひ知ってほしいのが、アルコールの代謝と栄養の関係です。
実は、お酒の影響を最小限に抑えるには、「どんな栄養素が不足しやすいのか」「自分の体質がどうなのか」を理解することがとても重要です。
この記事では、アルコール代謝の仕組みとともに、酔いや悪酔いを防ぐための栄養対策を、分かりやすく解説していきます。
アルコールはどうやって分解される?
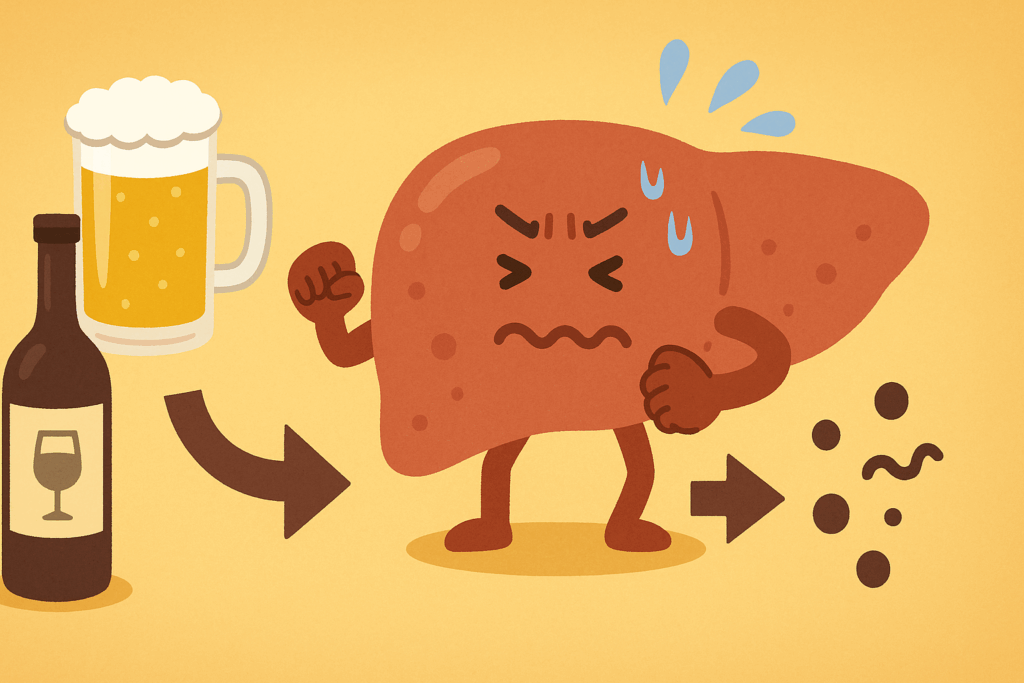
まず、お酒に含まれるアルコールは、体内で次のような順序で分解されていきます。
- アルコール → アセトアルデヒド
肝臓の酵素「アルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)」によって分解されます。
※このアセトアルデヒドが、二日酔いや悪酔いの主な原因。 - アセトアルデヒド → 酢酸
次に「アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)」という酵素が働き、毒性のあるアセトアルデヒドを無害な酢酸へと変えます。 - 酢酸 → 炭酸ガスと水
筋肉などで代謝され、最終的には呼気や尿として体外に排出されます。
酔いやすい・酔いにくいは「体質」で決まる
「すぐ顔が赤くなる」「少量で気持ち悪くなる」という方は、ALDHの働きが弱い体質かもしれません。これは遺伝的なもので、大きく以下の3タイプに分かれます。
- 活性型:酵素がしっかり働くタイプ
- 低活性型:分解が遅く、酔いやすい
- 非活性型:ほぼ分解できない
日本人の約40〜50%が「低活性型または非活性型」だと言われています。
親が「お酒に弱い体質」であれば、子どももそうである可能性が高いです。
自分のタイプを知るには、「アルコールパッチテスト」などが有効です。

アルコールは栄養素じゃない?
アルコールについてもっと知りたい方はこちらもご覧ください
お酒を飲むと不足する栄養素とは?
アルコールを分解するには、酵素を作るための材料=栄養素が必要です。
特に不足しやすいのが以下の2つ。
- 亜鉛(Zn)
アルコールをアセトアルデヒドに変える「ADH酵素」の主成分は亜鉛です。年齢とともに体内の亜鉛量は減っていき、60代では20代の1/10ほどに。
さらに高齢になると300分の1以下になることもあります。お酒をよく飲む人ほど、意識して摂るべき必須ミネラルです。
おすすめの摂取量:1日30mg程度(食事+サプリ) - ビタミンB群(特にB6・B3)
アセトアルデヒドを酢酸に分解する酵素反応には、「NAD⁺」という補酵素が必要です。これはビタミンB3(ナイアシン)から作られます。
また、ビタミンB群は単独では作用しにくく、B1・B2・B6・B12など複数のビタミンをまとめて摂取することが重要です。
おすすめは「ビタミンB50コンプレックス」のようなマルチタイプのサプリメントです。
飲酒がストレス解消になっていませんか?
最近では「お酒がストレス発散の手段になっている」という方も多く見られます。
しかし、実はお酒を飲みすぎると、脳内のセロトニン生成が低下し、気分が落ち込みやすくなります。
これは悪循環で、セロトニン不足 → ストレス → 飲酒 → さらに不足…というサイクルに。
うつ傾向のある方や、不眠に悩んでいる方は、まず「アルコールを控える」ことが大切です。
食事指導やメンタルケアに関わる方も、この視点を意識してみてください。
飲酒による「落とし穴」と対策
- 空腹時の飲酒はNG
→ 胃や小腸で一気に吸収されてしまい、肝臓への負担が増します。
→ 食事と一緒に摂ることで吸収を穏やかにできます。 - 「汗でアルコールを抜く」は迷信
→ 実際に汗から排出されるのはアルコールの5%未満です。 - 胃の手術を受けた方は特に注意
→ アルコールが一気に小腸に流れ込み、悪酔いや負荷が強くなります。
お酒とうまく付き合うために
お酒を楽しむには、「体質」と「栄養」の両方を意識することが大切です。
以下のポイントを抑えて、健康的に付き合っていきましょう。
- 自分の代謝タイプを知る(パッチテスト推奨)
- 亜鉛・ビタミンB群を意識して補う
- 空腹で飲まない・食事と一緒に摂る
- 翌日に残さないよう、事前にケアする
